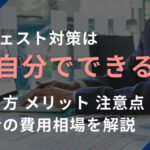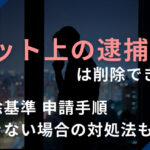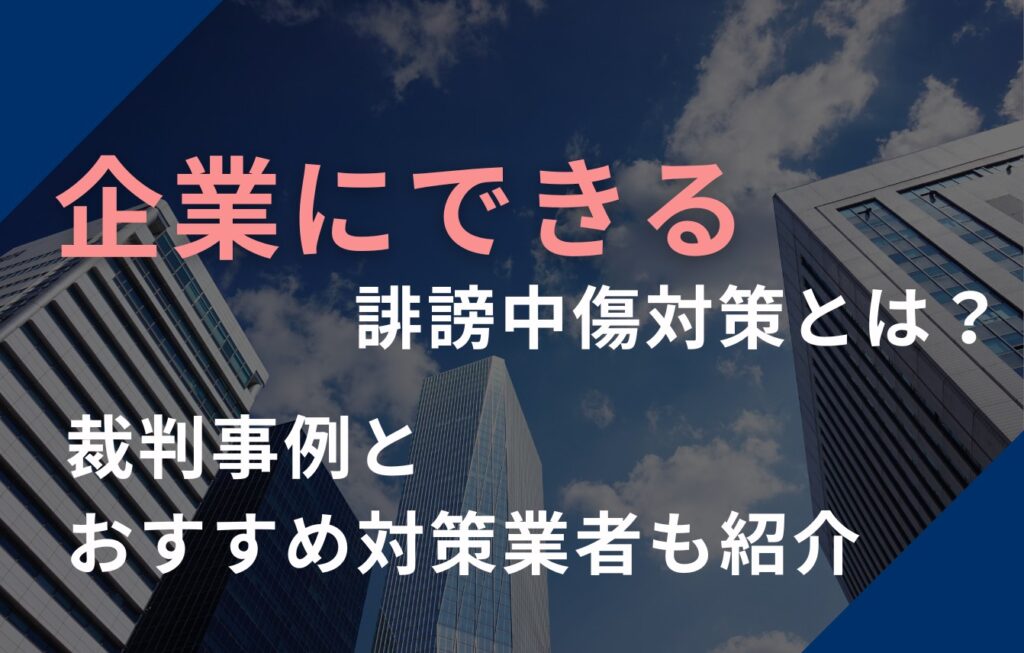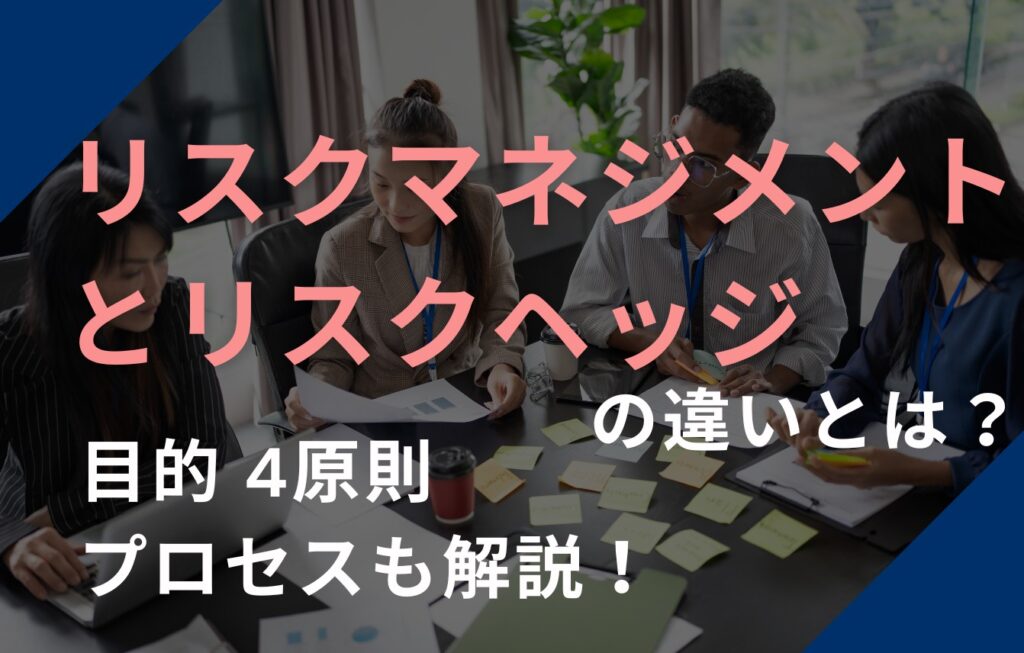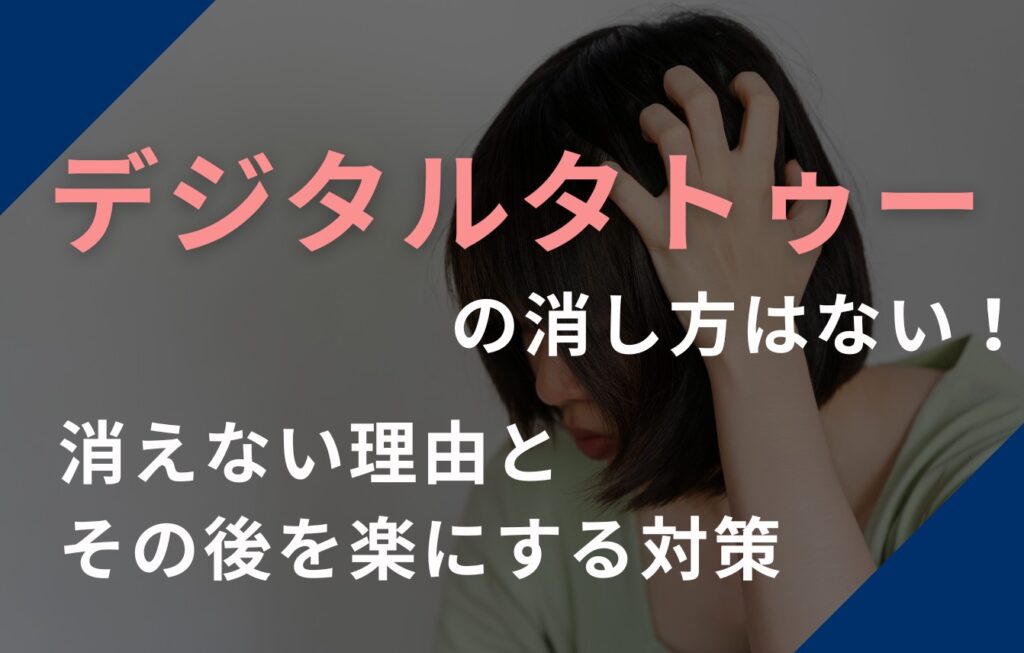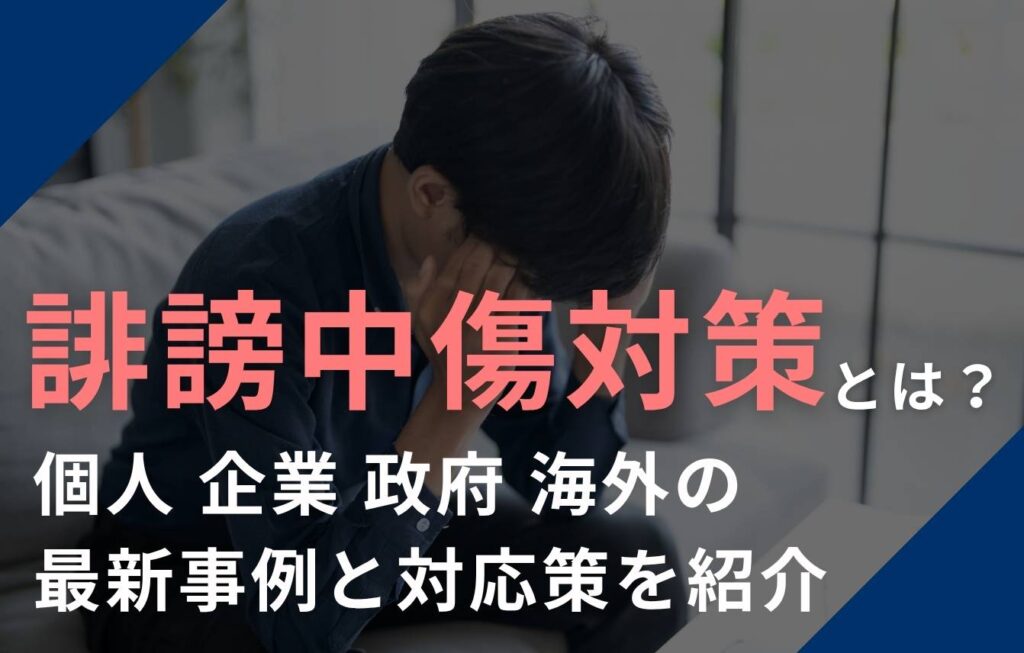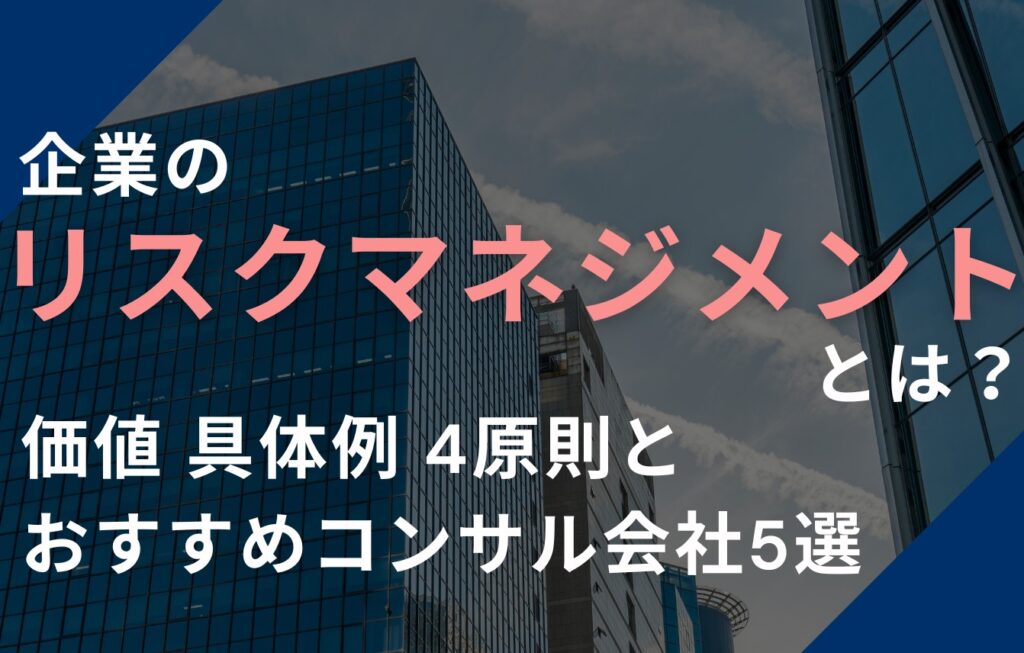レピュテーションリスクとは、簡単に言うと企業の評判が損なわれるリスクのことです。
SNSの拡散力や検索エンジンの影響が強まる現代において、企業の信用は一夜にして崩れることがあります。たとえ事実無根の情報でも、一度悪評が広まれば顧客離れや業績悪化、株価の下落など深刻な事態を招きかねません。
この記事では、レピュテーションリスクの基本的な意味や類語を紹介します。また、企業で実際に起こった事例や発生原因、具体的な対策方法も解説します。
レピュテーションリスクへの理解を深め、自社の信頼を守りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
CONTENTS
レピュテーションリスクとは?
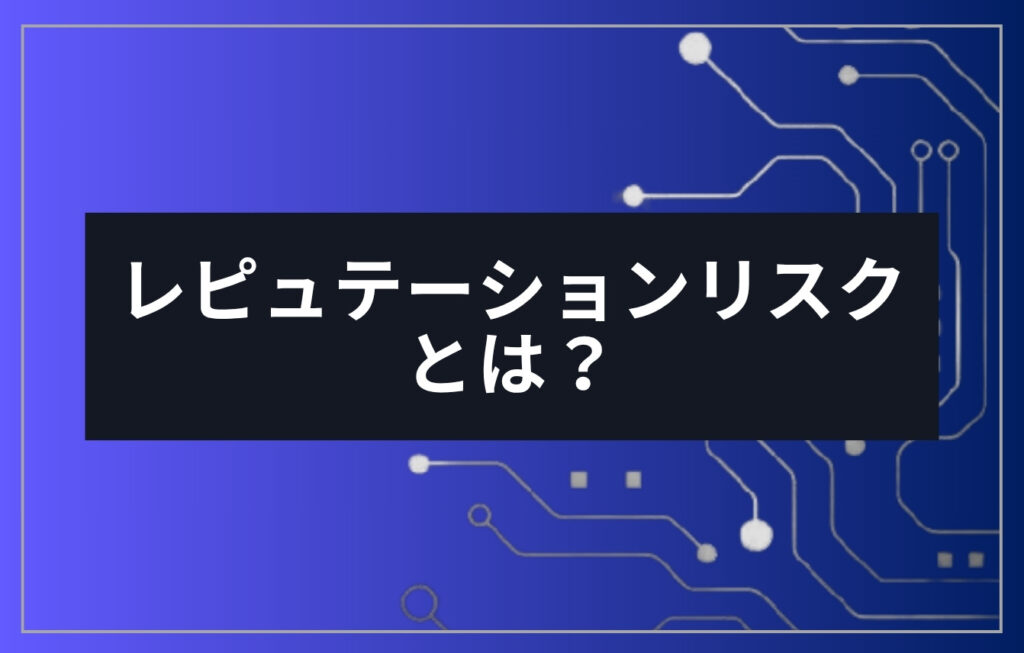 企業が抱えるリスクのなかでも、近年特に注目されているのがレピュテーションリスクです。
企業が抱えるリスクのなかでも、近年特に注目されているのがレピュテーションリスクです。
ここでは、レピュテーションリスクの英語での表現方法、実際の使い方や例文まで、具体的に解説していきます。
レピュテーションリスクの英語の意味
レピュテーションリスクは英語で「reputation risk」と書き、日本語に言い換えると「評判リスク」や「風評リスク」のような意味があります。- 評判リスク
- 風評リスク
- 企業イメージリスク
- 名誉毀損リスク
- 社会的信用リスク
また、レピュテーションリスクと似た言葉には、以下のようなものがあります。
| 混同しやすい言葉 | 詳細 |
| レピュテーショナルリスク | レピュテーションリスクと同じ |
| オペレーショナルリスク | 業務遂行上の問題 |
| コンプライアンスリスク | 法令・規定違反による損害 |
レピュテーションリスクの使い方と例文
レピュテーションリスクは、ビジネスシーンでも頻繁に使われており、主に「信用にかかわるリスク」として、危機管理や広報戦略の文脈で用いられます。- レピュテーションリスクを最小限に抑える体制を整えましょう
- この施策は顧客の反発を招き、レピュテーションリスクを高めかねません
- 社内の不祥事が原因で、企業全体のレピュテーションリスクが高い状態です
- SNS運用においては、常にレピュテーションリスクを意識すべきです
- 風評被害を放置すると、レピュテーションリスクにつながる恐れがあります
- 危機管理マニュアルには、レピュテーションリスクへの対応も含まれています
企業にはレピュテーションマネジメントが求められている
企業にとってレピュテーションマネジメントが求められている理由は、以下の通りです。- 評判が企業価値や経営そのものに直結する時代だから
- 企業の情報が誰でも発信・拡散できるようになったから
- 一般人の投稿で炎上する可能性があるから
- サービスミスなども一気に広まり、信頼失墜につながるから
評判は守る時代から戦略的に管理する時代へと変わっており、マネジメントの導入は企業の持続的成長に不可欠です。
企業リスクを今すぐ解決!逆SEOとサジェスト対策に特化した実績で、貴社のブランドを守るアクシアカンパニー。過去1200件以上の成功事例と業界トップクラスの成果を誇ります。売上・採用・ブランドを守るための最適解を提供している専門会社です。
レピュテーションリスクの発生原因
 レピュテーションリスクは、多様な要因から生まれます。
レピュテーションリスクは、多様な要因から生まれます。
内部告発や炎上、不祥事だけでなく、事実無根のデマやネット上の風評も無視できません。それぞれの原因を具体的にみていきましょう。
内部告発・情報漏洩
企業の評判を揺るがす原因の1つに、内部告発や情報漏洩があります。企業内部の不正や劣悪な労働環境が明るみに出ることで、社会からの信頼を失うきっかけになります。たとえば、食品偽装や建築基準法違反のような問題が従業員によって告発された場合、世間は企業の体質そのものに疑問を抱くでしょう。
さらに、情報漏洩によって顧客情報や企業の機密が外部に流出すれば、損害賠償や顧客離れにも直結します。
こうした事態は、告発者への共感や擁護の声が強まり、企業側への批判が一層激化する傾向があります。事実であればもちろん、仮に誤情報であっても評判の損傷は免れません。
バイトテロ・バカッター
バイトテロやバカッターと呼ばれる行為も、企業にとってレピュテーションリスクの原因となります。アルバイトや若年層の従業員が店舗内で不適切な言動を行い、その様子をSNSに投稿して炎上するケースです。
たとえ一部の従業員の軽率な行動であっても、企業全体の管理体制や教育方針が批判の的になります。
さらに、ネット上に一度拡散された動画や画像は、後から削除しても完全には消えず、企業のブランドイメージに長期間ダメージを与える可能性があります。
デマ・誹謗中傷
事実に基づかないデマや誹謗中傷も、企業の評判を揺るがすレピュテーションリスクの要因です。企業が問題を起こしていないにもかかわらず、「あの会社はブラックらしい」「異物混入があったらしい」など、根拠のない噂がSNSや掲示板で拡散されるケースがあります。
虚偽情報は、真実と区別がつかず、瞬く間に広まり、信頼の失墜や売上減少を招く恐れがあります。
一度広まった誤情報は完全に消すことが難しく、企業にとって長期的なダメージとなりかねません。対策を怠れば、事実無根の話がいつの間にか事実として認識されてしまうこともあります。
ネット風評被害
ネット上の風評被害は、企業にとって深刻なレピュテーションリスクを引き起こす原因の1つです。実際に問題が起きていなくても、SNSや匿名掲示板、転職サイトの口コミなどにネガティブな情報が書き込まれるだけで、企業の信頼は簡単に揺らぎます。
サジェスト汚染と呼ばれる現象では、企業名を検索した際に「ブラック」「やばい」「倒産」などの関連ワードが表示され、悪印象を与えるでしょう。
風評被害は放置すればするほど定着し、集客や採用、取引にも悪影響を及ぼします。被害の元が個人の感想や事実無根の書き込みであっても、信じる人が増えればそれ自体がリスクとなります。
コンプライアンス違反によるSNS炎上
企業公式のSNSアカウントでのコンプライアンス違反は、レピュテーションリスクを顕在化させる要因です。差別的な表現や事実に基づかない情報発信、不適切な炎上商法的投稿などがSNS上で非難を浴び、瞬く間に拡散される事例があります。
企業が発信者であるだけに、「公式の立場で何を言っているのか」と、社会からの批判はより厳しくなります。
一度炎上すれば、投稿の削除だけでは収まらず、謝罪対応や広報活動に多くのリソースを割く必要があるでしょう。また、過去の投稿も掘り返され、さらに被害が拡大するケースもあります。
従業員・役員の不祥事
企業のレピュテーションリスクを高める原因として、従業員や役員の不祥事は深刻です。役員による横領やインサイダー取引、従業員によるセクハラ・パワハラ、顧客情報の不正利用などは、刑事事件として報道されることもあり、企業の信頼を大きく損ないます。
不祥事が起きた本人が退職や謝罪をしても、企業イメージの回復には時間がかかるでしょう。
さらにSNSで拡散されれば、情報は半永久的にネット上に残り続け、将来的な取引や採用にも悪影響を及ぼします。
不祥事が個人の行為であっても、世間は企業全体のガバナンスや企業体質に問題があると受け取る傾向があるため、無関係とはいえません。
商品・サービスの問題
商品やサービスに関する問題も、企業のレピュテーションリスクを高める要因となります。近年では、商品に欠陥があったり、接客態度が悪かったりした場合、それを体験したユーザーがSNSで不満を発信し、悪評が広がるケースが増えています。
「料理が冷めていた」「説明と違う商品が届いた」といった声が繰り返されると、企業の品質に対する信頼そのものが揺らぐでしょう。
さらに、価格と品質のバランスに納得できないと感じた消費者は、他社製品や競合サービスに流れることも珍しくありません。サービス提供後の対応が悪ければ、リピーター離れも進みます。
同業者の炎上
自社が直接関与していなくても、同業他社の不祥事や炎上が原因でレピュテーションリスクが高まることがあります。たとえば、ある飲食チェーンで異物混入が発覚した場合、似たような業態の他社店舗も「同じようなことがあるのでは」といった不安を持たれ、来店を控える人が出てくるでしょう。
実際に、すき家でネズミが目撃された動画が拡散された際、同じ牛丼チェーンである吉野家や松屋にも影響が及んだとされています。
このように、業界全体が「危ない」「信用できない」といった印象を持たれると、売上やブランド評価に悪影響が出ます。
自社の評判を守るには、他社の炎上に無関心ではいられません。
企業リスクを今すぐ解決!逆SEOとサジェスト対策に特化した実績で、貴社のブランドを守るアクシアカンパニー。過去1200件以上の成功事例と業界トップクラスの成果を誇ります。売上・採用・ブランドを守るための最適解を提供している専門会社です。
レピュテーションリスクが高いとどうなる?7要素で解説
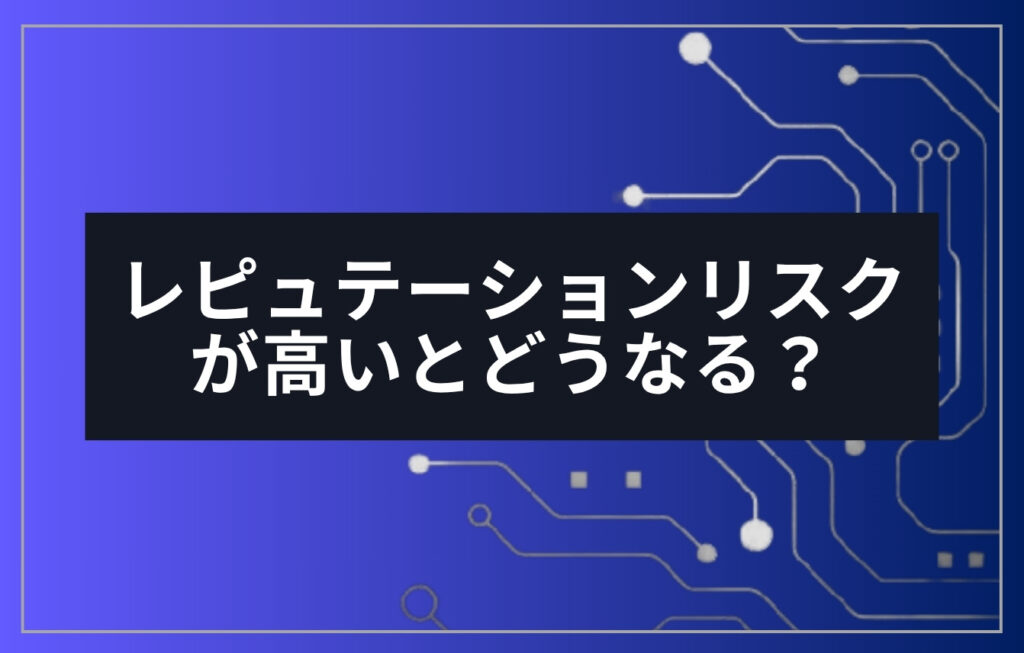 レピュテーションリスクが高まると、製品への信頼低下や職場環境の悪化、経営層への不信感など、企業全体に深刻な影響を及ぼします。
レピュテーションリスクが高まると、製品への信頼低下や職場環境の悪化、経営層への不信感など、企業全体に深刻な影響を及ぼします。
ここでは、損保総研『レピュテーション・リスクと保険 (第127号 2019.5)』にある7つの要素を元に、レピュテーションリスクが高まることでどのような影響があるか解説します。
①製品・サービス
製品やサービスに関するトラブルは、企業のレピュテーションリスクを大きく左右します。具体的な例は以下の通りです。
- サービスに対するクレームや不満がSNSや口コミサイトで拡散された
- 食材の質や接客態度への批判が連鎖的に広まった
このように、製品やサービスの質が低下すると、顧客の期待を裏切ることになり、ブランド価値の低下を招きかねません。
そのため、日頃から品質管理の徹底や迅速なクレーム対応を行い、顧客満足度を維持することが重要です。
②革新
革新の遅れは、企業のレピュテーションリスクを高める要因となります。具体的な例は以下の通りです。
- 管理職の戦略的判断が遅れた
- 市場の変化に対応できなかった
- 競合他社が次々に新技術や製品を市場に投入する中で、自社の製品が遅れを取った
革新性が疑われると、企業の成長性や将来性に不安が広がり、信頼を損ねる結果となります。
継続的な技術開発や迅速な経営判断を行い、市場の期待に応えることが必要不可欠です。
③職場
職場環境に関する問題は、企業のレピュテーションリスクを深刻化させる要素です。具体的な例は以下の通りです。
- 従業員が退職後に「ブラック企業」といった悪評をSNSや口コミで広めた
- 職場でのパワハラやセクハラが内部告発された
- 安全衛生に関する苦情やコンプライアンス違反が明るみに出た
- 倫理的な雇用慣行の欠如や従業員の不正行為があった
したがって、企業は健全で安全な労働環境づくりに注力し、問題があれば迅速に対応することが不可欠です。職場の評判を守ることは、企業の持続的成長に直結しています。
④ガバナンス
企業のガバナンスに関する問題は、レピュテーションリスクの重要な要素です。具体的な例は以下の通りです。
- 法令違反が明るみに出て処罰や行政からの勧告を受けた
- 詐欺的なサービスや不正行為を疑われる口コミが広まった
- 規制違反による罰金や訴訟が報じられた
そのため、法令遵守の徹底と公正な経営体制の維持が不可欠であり、日頃から透明性の高い情報開示と倫理的な意思決定を心掛けることが必要です。
⑤市民
企業が地域社会や環境に責任を持たない場合、レピュテーションリスクが高まります。具体的な例は以下の通りです。
- 重大な人命に関わる事故を起こした
- 環境汚染や人権侵害に関する問題がメディアで取り上げられた
- 租税回避の疑いが持たれた
市民的責任を軽視すると社会的な反発を招き、事業活動に支障が出るリスクが高まるでしょう。
そのため、環境保護や地域貢献を積極的に推進し、透明性のある企業活動を心がけることが必要です。社会からの信頼を守ることは、企業の持続的発展に欠かせません。
⑥リーダーシップ
企業のリーダーシップに問題が生じると、レピュテーションリスクが高まります。具体的な例は以下の通りです。
- 経営陣の不祥事やスキャンダルが公になった
- 経営判断のミスによって事業が失敗した
- IT投資の失敗や不適切なインセンティブ設計があった
- 上級管理職の刑事訴追や規制措置が発生した
したがって、明確なビジョンを持ち、公正かつ透明な経営を行うことが不可欠です。これが企業の信頼維持と持続的成長に繋がります。
⑦パフォーマンス
企業の業績や成長性に問題が生じると、パフォーマンスに関するレピュテーションリスクが高まります。具体的な例は以下の通りです。
- 株主向けの説明会で業績悪化が判明した
- 成長の鈍化を元従業員や関係者が口コミで広めた
- 主要な契約を失った
- 巨額の無保険損失が発生した
このようなパフォーマンス低下は、企業の将来的な成長や競争力にも大きな打撃になりかねません。
透明性の高い情報開示と持続的な経営改善が、信頼回復と企業価値向上につながります。
企業リスクを今すぐ解決!逆SEOとサジェスト対策に特化した実績で、貴社のブランドを守るアクシアカンパニー。過去1200件以上の成功事例と業界トップクラスの成果を誇ります。売上・採用・ブランドを守るための最適解を提供している専門会社です。
レピュテーションリスクが高く風評被害になった事例
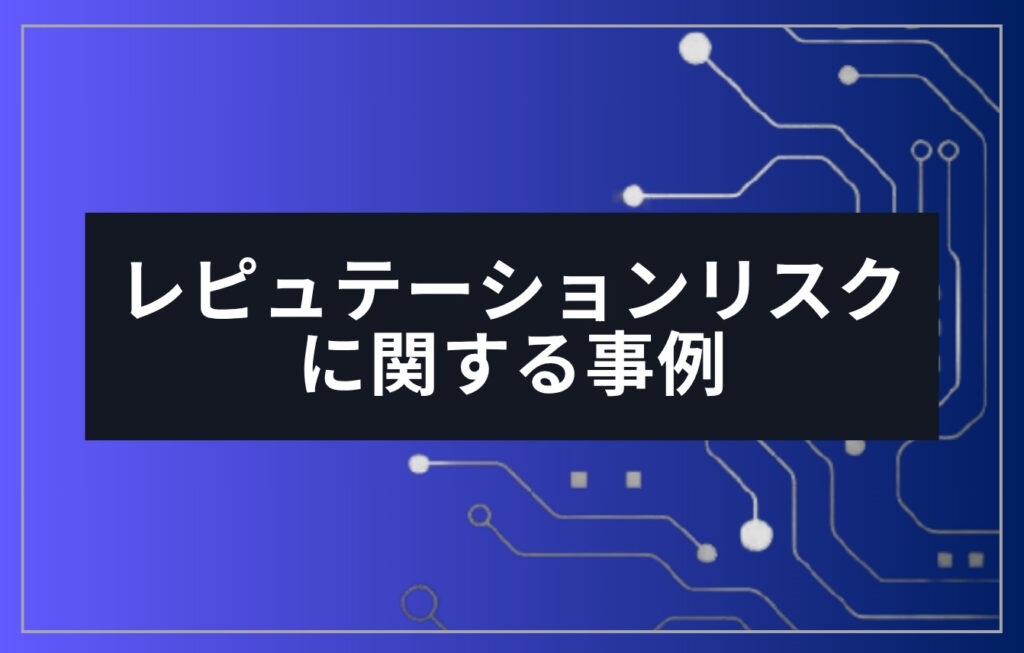 レピュテーションリスクによって実際に風評被害を受けた企業を5つ紹介します。
レピュテーションリスクによって実際に風評被害を受けた企業を5つ紹介します。
各事例から何が原因で評判が傷ついたのか、どのような影響が出たのかを詳しくみていきましょう。
以下の内容について一切の責任を負いません。
内容に関するご質問やご対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。
レピュテーションリスク事例:ユニクロ
ユニクロは大手アパレル企業として、過去にレピュテーションリスクが顕在化した事例があります。特に、労働条件とサプライチェーンに関する問題が注目されました。労働環境の問題では、親会社であるFast Retailingが工場労働者の賃金や労働時間管理に関して批判を受け、企業の評判に影響が出ました。
また、ユニクロの広範なグローバルサプライチェーンにおいても、労働条件の不備や環境負荷が指摘され、監査体制や透明性の強化が求められました。
これらの課題に対応するため、ユニクロはサプライヤー管理の改善やCSR活動の強化に取り組み、レピュテーションリスクの軽減を図っています。
ユニクロの事例は、企業が抱える多様なリスクを把握し、継続的に改善していく重要性を示しています。
レピュテーションリスク事例:かんぽ生命保険・日本郵便
かんぽ生命保険と日本郵便は、2024年に保険業法違反となる認可前の保険勧誘を計681件行ったことを公表し、大きなレピュテーションリスクに直面しました。この不正勧誘は、2024年1月発売の一時払い終身保険や2023年4月開始の学資保険など複数の商品に及び、約700人の社員が関与していたとされます。
認可前に顧客へ販売説明を行う行為は法律違反であり、企業の管理体制やコンプライアンスの甘さが露呈した事例です。
不祥事は金融庁の調査により明るみに出ており、かんぽ生命が2024年3月に一部を公表した後、追加調査でさらに多くの違反が判明しました。
こうした問題は企業の信用を大きく損ね、風評被害や顧客離れを招くリスクが高まるため、厳格な内部管理と再発防止策の強化が不可欠です。
レピュテーションリスク事例:みずほ銀行
みずほ銀行は2013年9月に金融庁から業務改善命令を受け、レピュテーションリスクに直面しました。この命令は、提携先の信販会社オリエントコーポレーションを通じた自動車ローンで反社会的勢力との取引が多数あったにもかかわらず、2年以上にわたり適切な対策を講じなかった点が問題視されたものです。
さらに、反社取引に関する情報が経営層に十分共有されていなかったことも指摘されました。
金融機関に対する業務改善命令は珍しいわけではありませんが、みずほ銀行の場合は大きく報道され、社会からの注目と批判を浴びる結果となりました。
この事例は、内部管理やガバナンスの不備が企業の評判にどれほど深刻な影響を与えるかを示しています。
レピュテーションリスク事例:ドミノピザ
ピザ宅配チェーンのドミノ・ピザジャパンは、2024年2月に従業員による不適切な動画拡散で大きなレピュテーションリスクに直面しました。動画には、従業員が鼻をほじった指でピザ生地に触れる様子が映され、SNSで瞬く間に拡散されて批判が殺到。公式アカウントを通じて謝罪し、動画に映った店舗を営業停止にするなど迅速な対応を取りました。
動画の生地は商品化されておらず、廃棄処分されています。また、関与した従業員には就業規則に基づく処分が行われ、法的措置も検討されました。
この事例は、従業員の行動が企業全体の信用に大きな影響を与え、SNS時代におけるリスク管理の重要性を示しています。
レピュテーションリスク事例:シャープ
シャープの公式X(旧ツイッター)でのレシピ投稿が、ネガティブな表現や考案者の紹介不足を理由に批判を浴びました。人気の電気自動調理鍋であるホットクックを使った一般ユーザー考案のレシピを紹介しましたが、「限界飯」「ずぼら飯」「まずまずうまい」など味に関する否定的な表現が不評を呼びました。
さらに、投稿にレシピ考案者への明確なクレジットがなかったことも問題視され、謝罪に追い込まれています。謝罪文では、表現の軽率さや紹介の遅れを認め、今後の広告企画から公式アカウントの関与を控えると表明しました。
しかし「私が」といった個人を強調する文言が逆に批判を招き、企業の公式アカウントとしての在り方に疑問の声も上がっています。この事例は、企業の公式発信における言葉選びや対応の重要性を示しています。
企業リスクを今すぐ解決!逆SEOとサジェスト対策に特化した実績で、貴社のブランドを守るアクシアカンパニー。過去1200件以上の成功事例と業界トップクラスの成果を誇ります。売上・採用・ブランドを守るための最適解を提供している専門会社です。
レピュテーションリスク対策にはマネジメントが必要
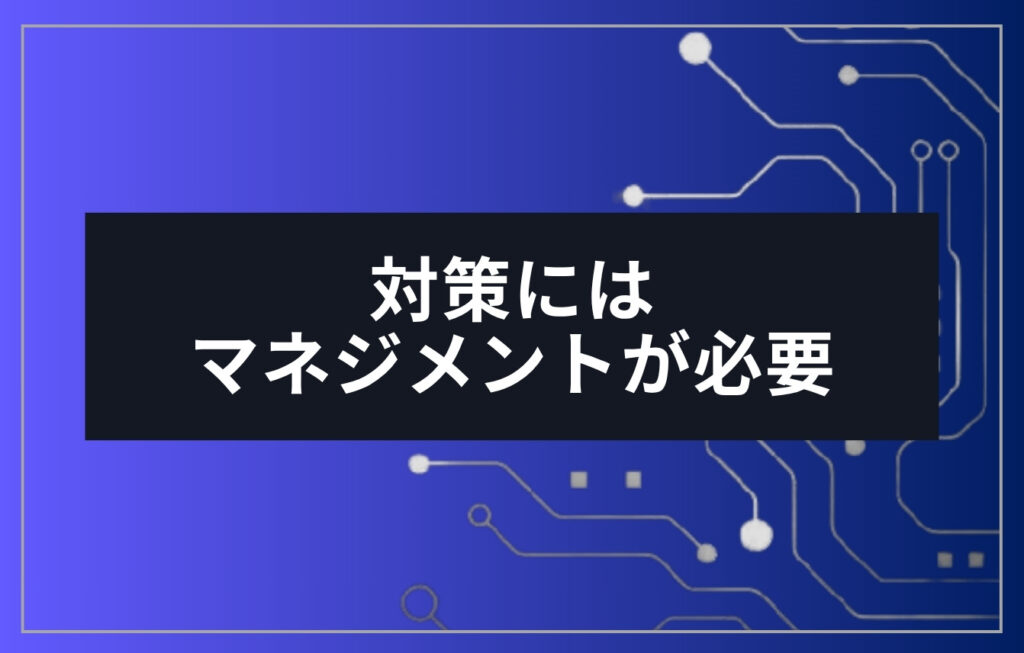 レピュテーションリスクを効果的に防ぐには、日常的なマネジメントが欠かせません。
レピュテーションリスクを効果的に防ぐには、日常的なマネジメントが欠かせません。
ここでは、把握・測定・回避といった具体的な対策に加え、保険による備えまで、実践的なアプローチを紹介します。
レピュテーションリスクの把握・評価
レピュテーションリスク対策の第一歩は、リスクの正確な把握と評価です。- 具体的な対策アクション
- SNSやメディアの動向をリアルタイムで監視
- 社内外からの情報収集を行う
- 従業員や関係者へのヒアリングを通じて事実確認を行う
SNSやメディアの動向をリアルタイムで監視し、ネガティブな情報の拡散状況を把握します。また、社内外からの情報収集を体系的に行い、リスクの程度や影響範囲を評価する体制を整えましょう。
レピュテーションリスクの測定・定量化
レピュテーションリスクを適切に管理するには、リスクの測定と定量化が欠かせません。- 具体的な対策アクション
- メディアやSNSでの自社に関する報道調査を行う
- 従業員や顧客を対象にアンケート調査を実施する
レピュテーションリスクの回避・低減
レピュテーションリスクの回避・低減には、計画的なマネジメントが欠かせません。- 具体的な対策アクション
- 危機管理体制を整備する
- 問題発生時に透明性のある説明会を開催する
- 広報や広告を通じて良好なブランドイメージを構築する
レピュテーションリスクの保険に入る
レピュテーションリスクの保険に入ると、万が一企業の評判が毀損した際に生じる経済的損失をカバーできます。- 具体的な対策アクション
- PR会社へのコンサルティング費用の補償
- リスクの予兆を察知して活動を行う際の費用
- ネガティブな情報が表面化する前に講じる予防策にかかる費用
また、危機発生前の段階でも、リスクの予兆を察知して活動を行う際の費用をサポートする保険プランも存在します。
事前の備えにより、企業の信用やブランド価値の低下を未然に防ぐ効果が期待できます。
レピュテーションマネジメントが企業を風評被害から守る
この記事では、レピュテーションリスクが高くなった場合の企業の影響に関して解説しました。革新や職場環境、ガバナンスなど、あらゆる側面から評判の低下が企業活動にダメージを与えます。実際の事例としてユニクロやみずほ銀行などのケースも紹介しました。
こうしたリスクを回避・低減するには、状況の把握や定量的な測定、適切なリスクマネジメントが重要です。
さらに、万が一に備えて保険に加入することも有効な対策です。信頼を守るため、平時からしっかり準備しましょう。